背面のほてり・首こり・不眠・ふらつきに悩む方へ
こんな症状、ありませんか?
- 背面や下半身が熱くなる/急な発汗
- 首のこり・後頭部の圧迫感/ふらつき・浮動性めまい
- 両手の感覚が鈍い/不眠・寝てもスッキリしない
- 緊張が抜けず、リラックスできない
これらは「自律神経の乱れ」によるものかもしれません。特に、交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、体は常に“警戒モード”になり、休息や回復がうまくいかなくなります。
リラックスできないのはなぜ?自律神経の乱れとその背景
「肩や首がずっと固い」「人前で緊張が抜けない」「夜に考え事が止まらず眠れない」「胃が重い」。
こうした不調は自律神経のバランスと深く関係しています。一般には交感神経が優位と説明されますが、近年はポリヴェーガル理論により、副交感神経のうち背側迷走神経が過剰に働くタイプの不調も注目されています。この記事では、体と心のメカニズムをやさしく解説し、今日からできるセルフケアを紹介します。
※医療的な診断・治療が必要なケースもあります。強い痛みや急な体調変化がある場合は医療機関にご相談ください。
ポリヴェーガル理論で見る自律神経の分類
自律神経とポリヴェーガル理論の基礎
近年注目を集めている「ポリヴェーガル理論」では、自律神経を〈交感神経〉と〈副交感神経〉に分け、さらに副交感神経を2つの系統に分類して捉えます。
以下の症状は、単なる「疲れ」や「気のせい」と片づけられがちですが、背景には自律神経のバランスの乱れがあることも少なくありません。
- 筋肉のこわばり・肩こり:慢性的なこりや痛みにつながります。
- 呼吸が浅くなる:息苦しさや焦燥感を感じることも。
- 心拍数・血圧の上昇:動悸や血圧の変動が起こります。
- 胃腸機能の低下:食欲不振、便秘・下痢など。
- 免疫力の低下:風邪をひきやすくなる、疲れが抜けにくい。
- 入眠困難:寝つきが悪くなる、眠りが浅くなる。
- ふらつき:足元が不安定になる。
- ほてり・のぼせ:顔や上半身が急に熱くなる。
交感神経:緊張・行動モード
活動や集中、危機への対応など「アクセル」の役割を担います。過剰になると肩こり、浅い呼吸、動悸、血圧上昇、胃腸不調、免疫低下、入眠困難などが現れます。
背側迷走神経:動けない・固まる反応
極度の危機にさらされたときに働く「シャットダウン」モード。過剰になると無気力や倦怠感、消化機能の低下などが現れます。
腹側迷走神経:安心とつながり
安全な環境で人とつながり、落ち着いて過ごすための「安心モード」。呼吸が整い、眠りやすくなり、人との関係もスムーズになります。

体・心に起こりやすい不調(症状と理由)
- 慢性の肩こり・首こり:交感神経優位で筋肉が常時緊張。
- 不眠・浅い睡眠:警戒モードが続き、副交感神経への切り替えが起きにくい。
- 胃腸の不調:ストレスホルモンが胃酸や腸の動きを乱す。
- 免疫低下:長期ストレスで免疫細胞の働きが鈍くなる。
- 血糖コントロールの乱れ:交感神経優位で血糖上昇→インスリン抵抗性。
- 無気力・解離感:背側迷走神経優位で省エネ状態が続く。
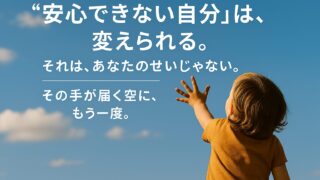
今日からできる自律神経セルフケア
① 肩の逆説的脱力ワーク
- 椅子に浅く座り、足裏を床に。
- 肩を耳に近づけるように5秒間ぎゅっと力を入れる。
- 息を長く吐きながらストンと下ろす。
- 2〜3回繰り返す。
- 最後に「今いちばん楽に感じる部位」へ注意を向ける。
② 意識的「大あくび」法
- 口を大きく開け、ゆっくり息を吸いながらあくびの動作を真似る。
- 目の奥・喉・顎を緩めるイメージで2〜3回。
③ 安全感の再教育(環境編)
- 照明を少し落とす/静かな音を流す/温かい飲み物を一口
- 背中にクッション、膝にブランケットなど安心感を増やす
- スクリーンから目を離し、遠くを見る
④ 注意点
- めまいや強い痛み、顎関節の症状がある場合は無理をしない。
症状が続く・悪化する際は医療機関へ。セルフケアは治療の代替ではありません。
自律神経に関するよくある質問
Q. すぐに効果を実感できません。
A. 神経系は学習システム。小さな安全を反復して積み重ねるほど、切り替えが上手になります。
Q. 背側迷走神経優位かどうか見分け方は?
A. 無気力・省エネ感・社会的関わりの減少・消化低下がヒント。専門家に相談し、身体感覚の安全づくりから始めるのがおすすめです。
自律神経とリラックス|まとめと次の一歩
- 自律神経の不調は、交感神経優位だけでなく背側迷走神経優位もあります。
- 肩の逆説的脱力、意識的あくび、環境づくりで「体から安全を学び直す」のが近道です。
- 免疫・胃腸・血糖・慢性痛など全身の不調に関わるため、日々の小さな習慣が大切です。
自律神経の乱れが続くと、「どうしたら良いのか分からない」と感じてしまうことは珍しくありません。ひとりで抱えるほど、緊張のスイッチは戻りにくくなります。
サロンでは、神経が安心しやすくなるように、マインドフルネスや呼吸法などを用いて優しくアプローチしています。身体が落ち着きを取り戻しやすい状態づくりをサポートする内容です(医療行為ではありません)。
緊張しやすい神経が少しずつ安心を思い出せるよう、負担のない方法でサポートしています。
[btn class=”btn-primary” url=”https://healing33.com/toiawasehakotira/” target=”_blank”]ご予約・お申込み / お問合せ[/btn]



コメント